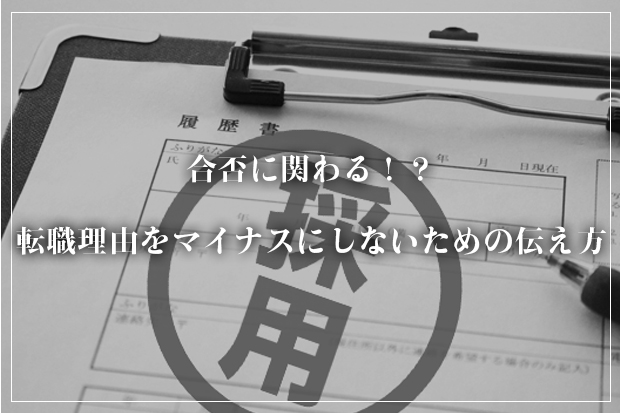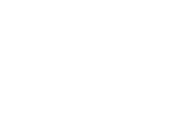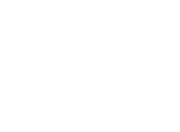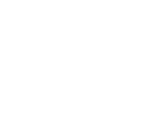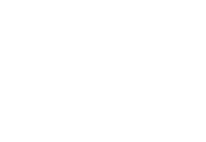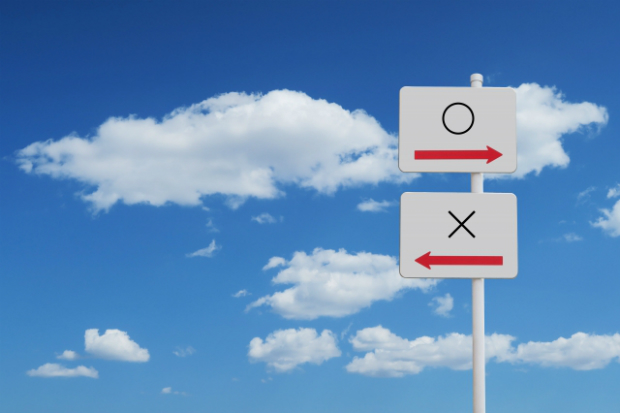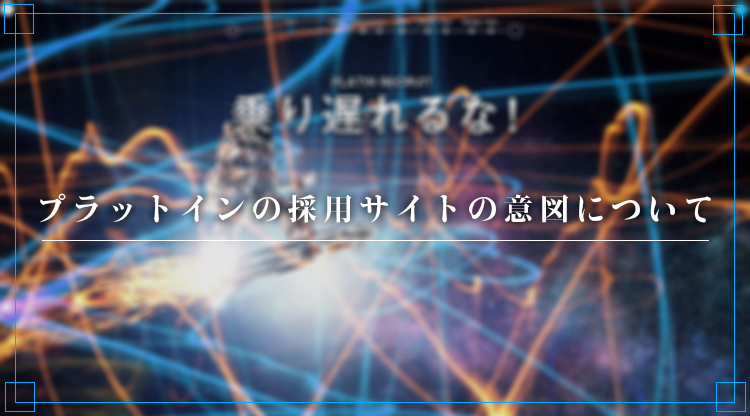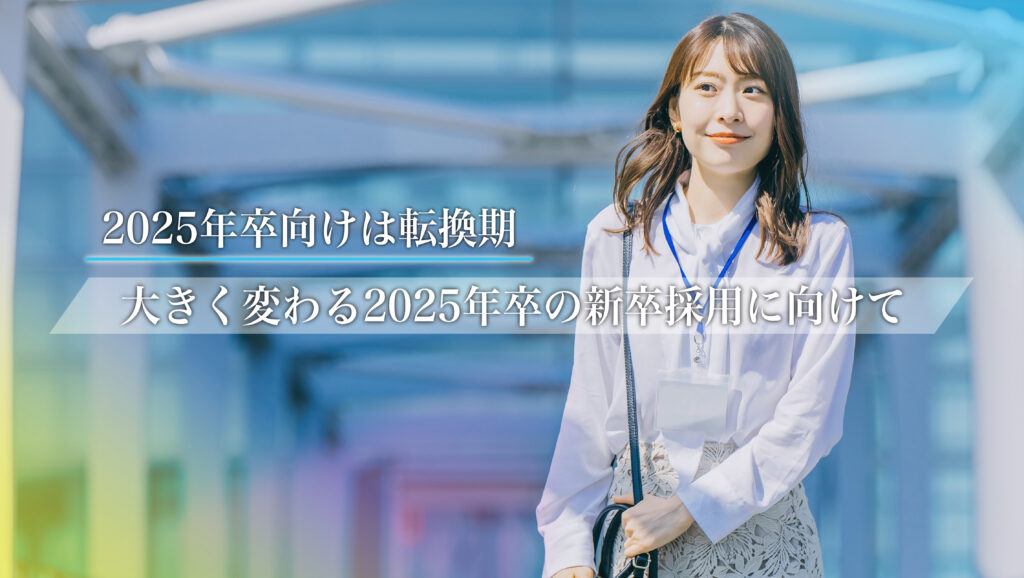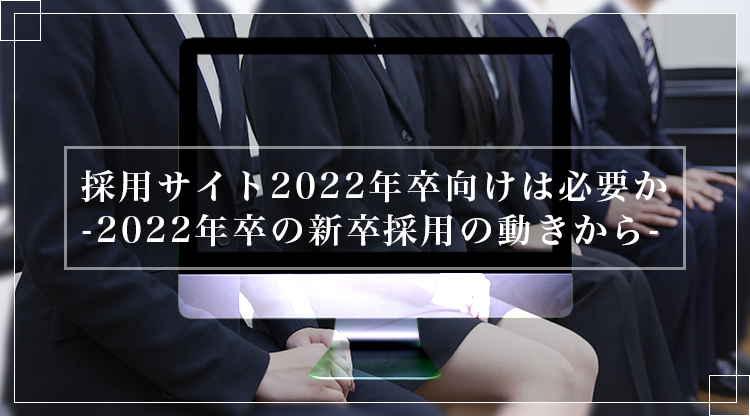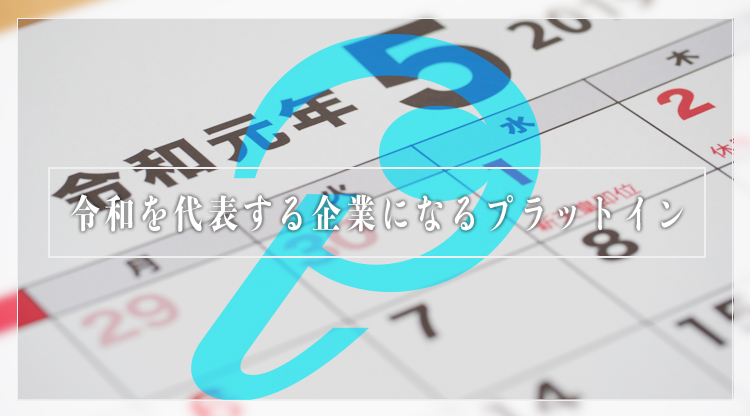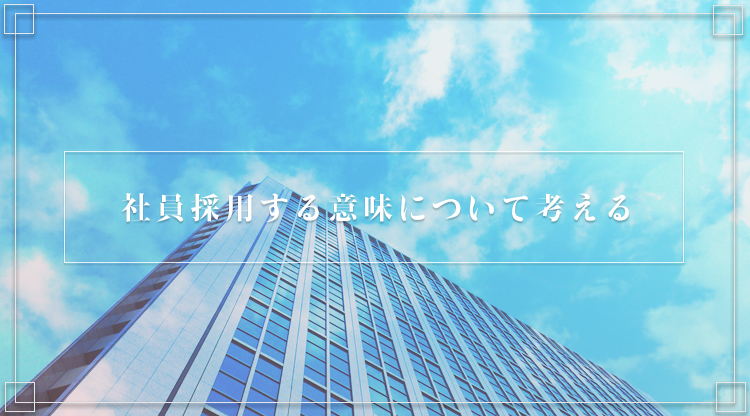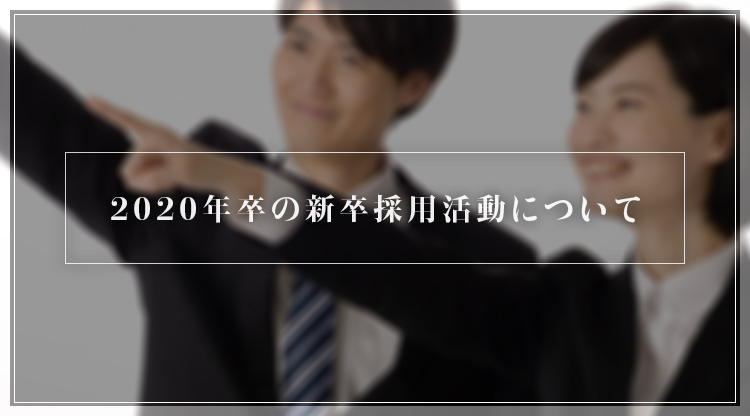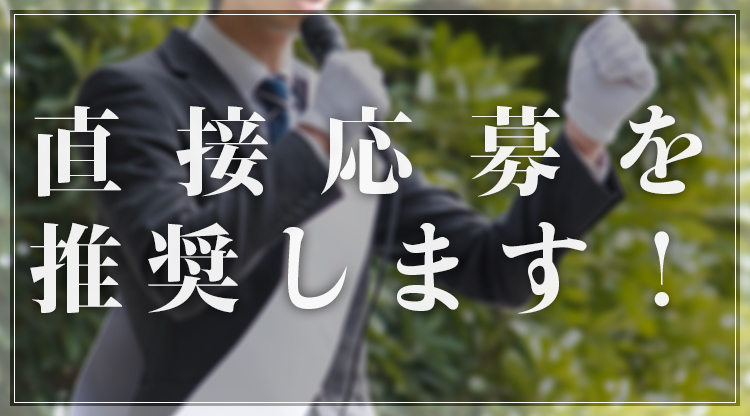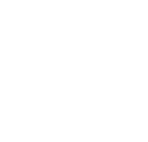
1.転職理由から何を探ろうとしているのか

まず1つめは「問題を起こすような人物かどうかを判断するため」です。実際にトラブルを起こして退職した場合はもちろんのこと、条件次第で簡単に担当業務を投げ出して応募してきていないか、些細なことに不満を募らせワガママいっぱいで辞めていないか、といった点を確認するために退職理由を聞くのです。そして、もし上記に該当するような理由なら「ウチに入れても問題を起こす恐れが高い。それならはじめから採用しないでおこう」という考えになるのです。
2つめは価値観や仕事観の確認です。仕事を辞めるからには何かしら不満があるのは当然で、問題はその不満がどの程度のレベルで爆発するのかを確認したくて退職理由を質問します。例えば、新卒で就職した会社を「やりたい仕事をやらせてもらえない」という理由で1年足らずで辞める若者が結構いますが、これでは「はじめから好きな仕事ばかりやらせてもらえると思っているのか?そんな考えの甘いヤツはいらない!」とばかりに不採用になってしまいます。
3つめはモチベーションの確認です。転職をする人の中には、図らずも前職場を辞めることになってしまったという人も少なからずいます。そうした人達に対し、気持ちを切り替えて前向きに仕事に取組んでもらえるのか、それとも未だに不満や恨みを抱えているのかを確認するために「なぜ辞めたのか」と質問します。この質問に対し前職場の愚痴や文句を長々と述べるような人物は「こんなに負のオーラが出ている人を入れては職場のみんなが迷惑してしまう」と受け取られ、やはり不採用となってしまいます。