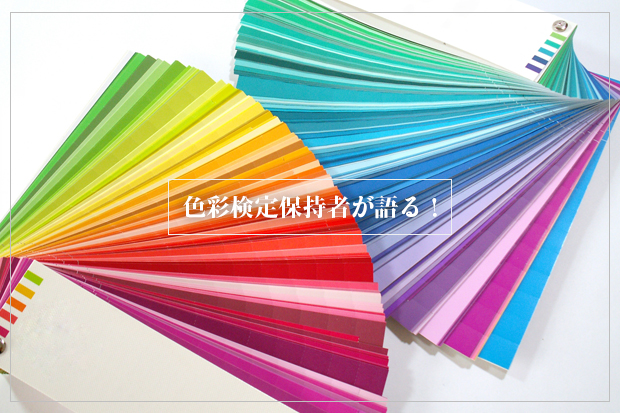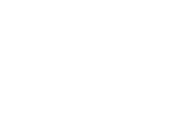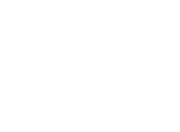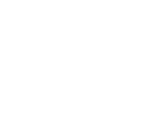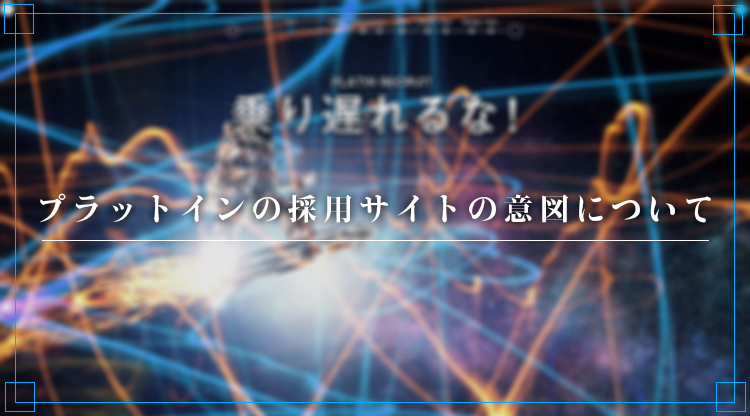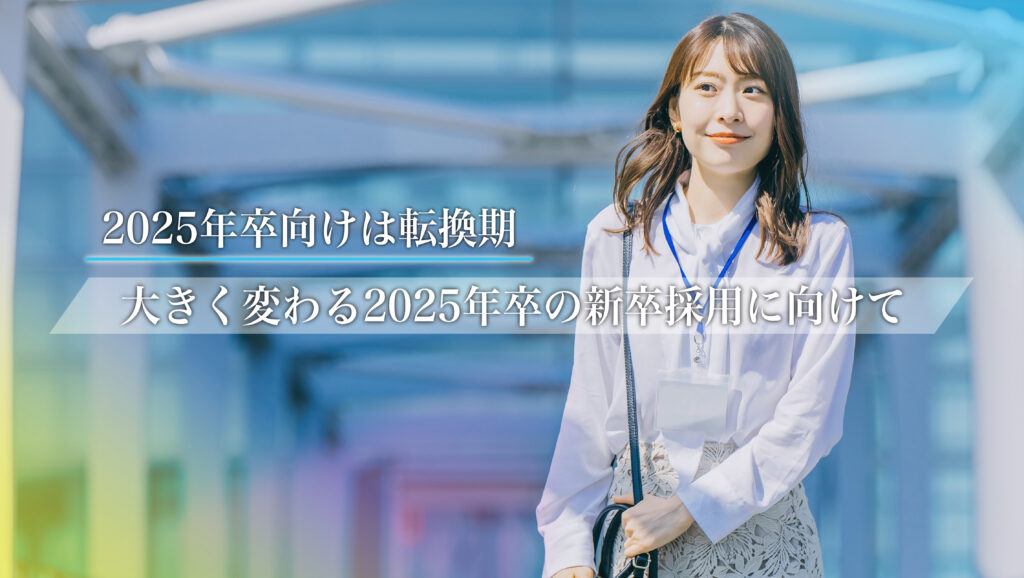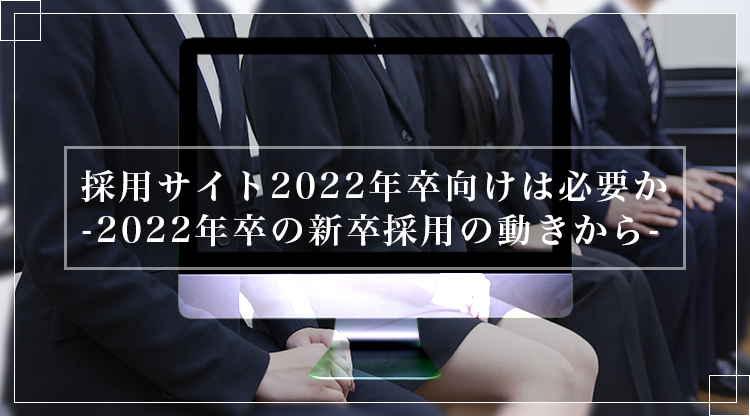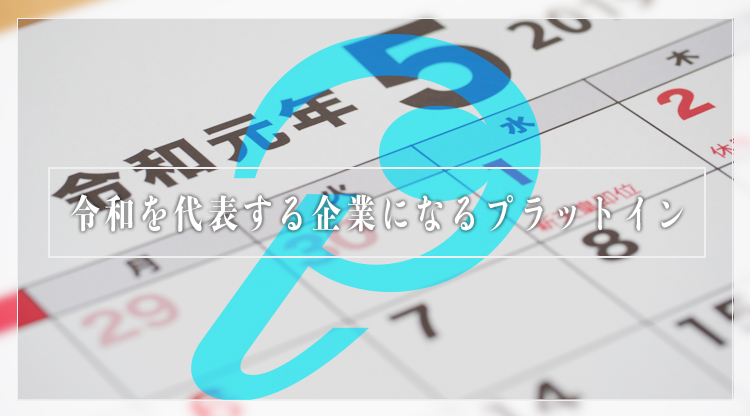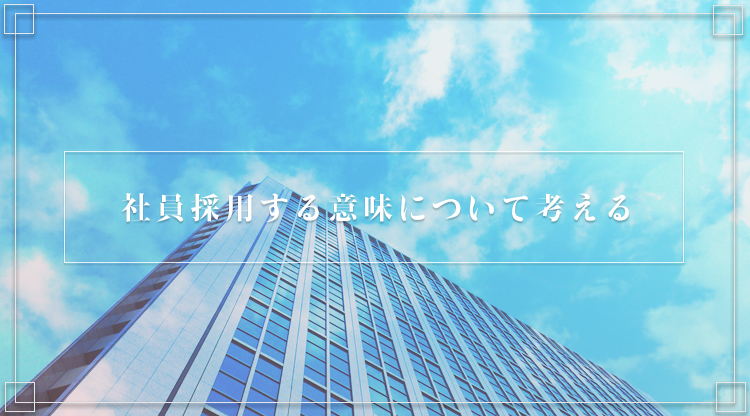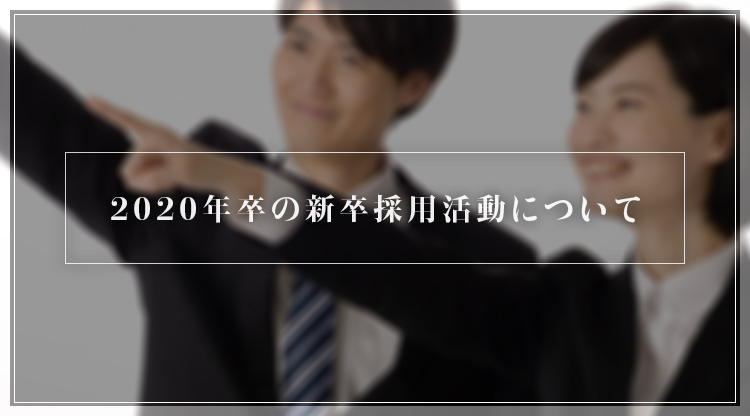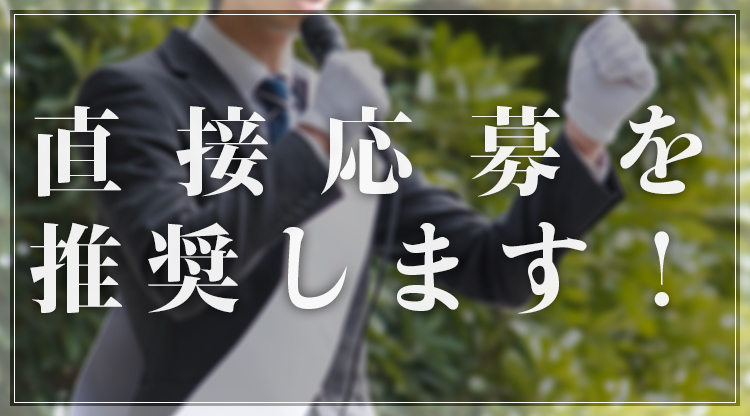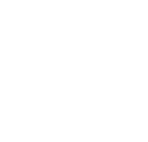
1.色彩検定とはどんな検定?

一番役に立ったと実感していることは、服とカバンとアクセサリーの色合わせができるようになったので、買い物の際、失敗をしなくなった(買ったのに使わないなどの無駄がなくなった)ことです。また家の壁や床の色から家具を選んだのですが、配色の力を利用して部屋に落ち着きと広さをより感じるようにしたところ、部屋が更に快適になり、今まで以上にくつろげるようになったことも役立ったこととして挙げることができます。あと料理を盛り付ける際、食器の色を合わせることで、料理が美味しそうに見えて、食卓に華を添えることができるようになりました。これは些細なことかもしれませんが、生活をより豊かにするという意味では役に立っていると思います。
このように色彩検定は、公私ともに役に立つ資格です。しかも一時的に役に立つ、というものではなく、一生自分の生活に彩を添えてくれるという素晴らしい資格なのです。更に(当たり前ではありますが)、履歴書に書くこともできます! 2・3級は年に2回受検が可能ですし、初心者でも取り組みやすい内容となっています。興味がある方はまず、2・3級から受験をされてみてはいかがでしょうか。色彩検定は大手書店でテキストや過去問題が販売されているので、受験勉強がはじめやすいことも魅力の一つですよ。