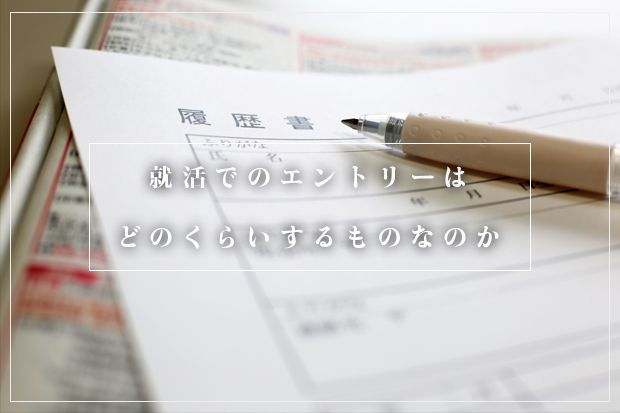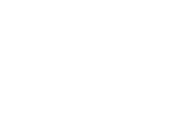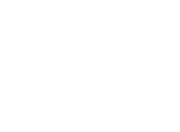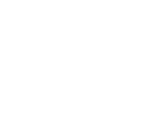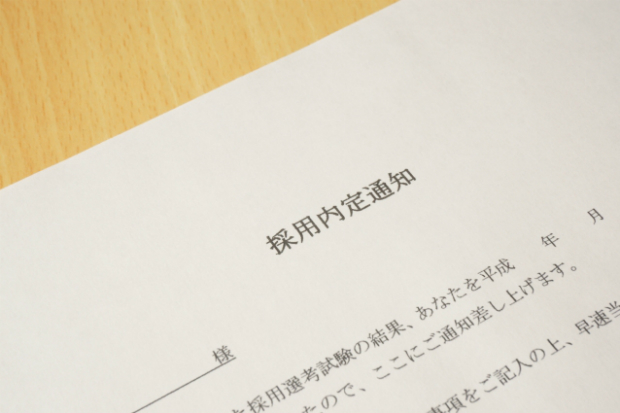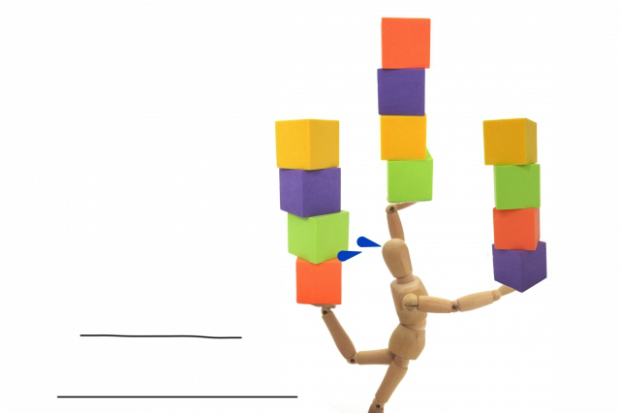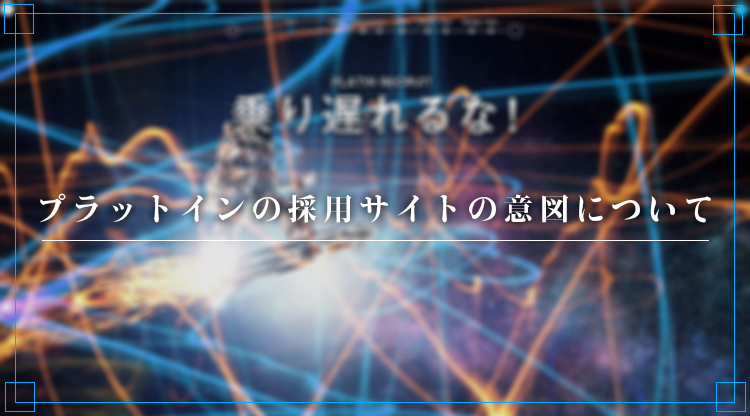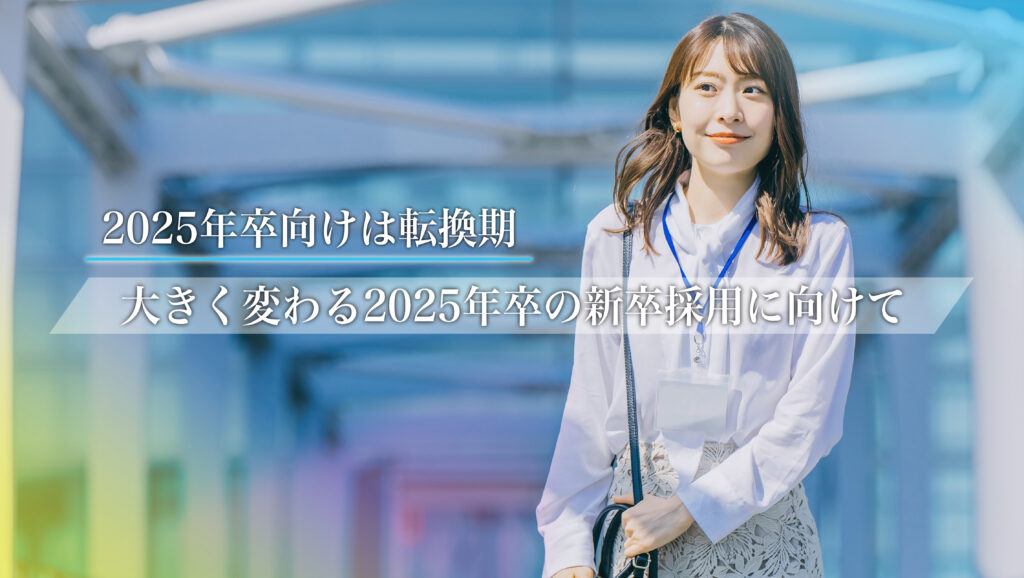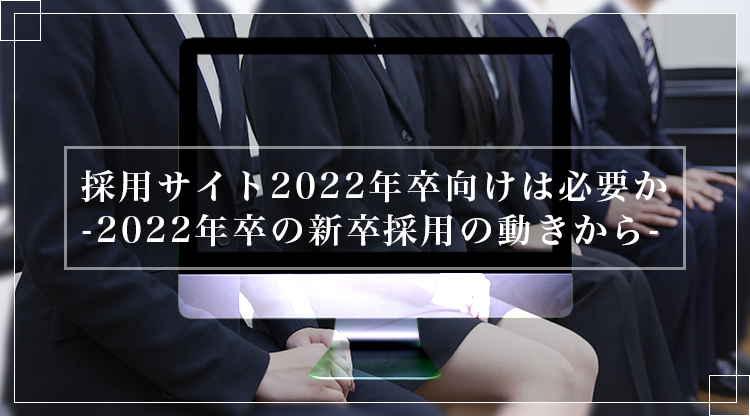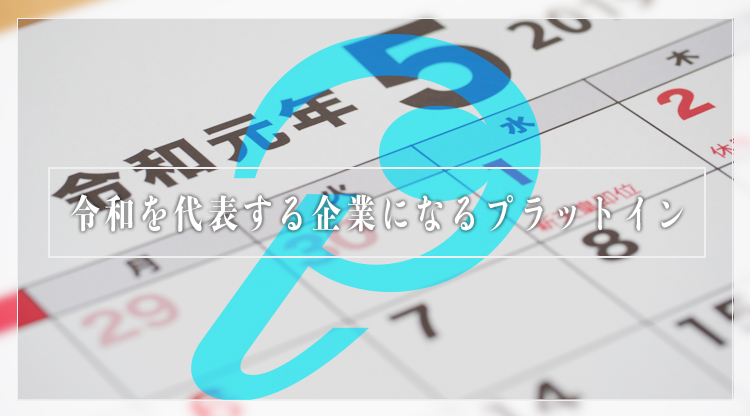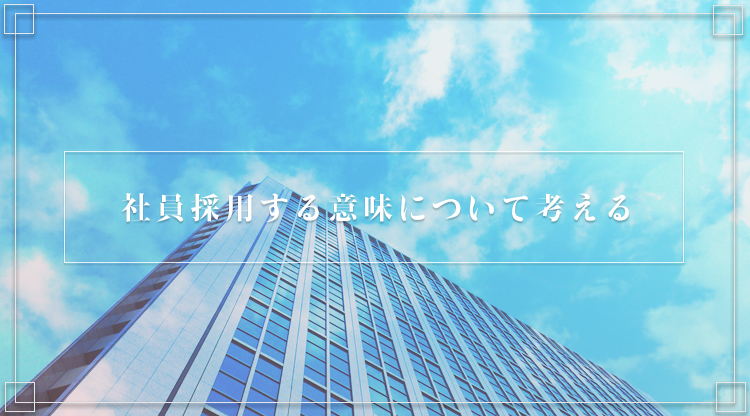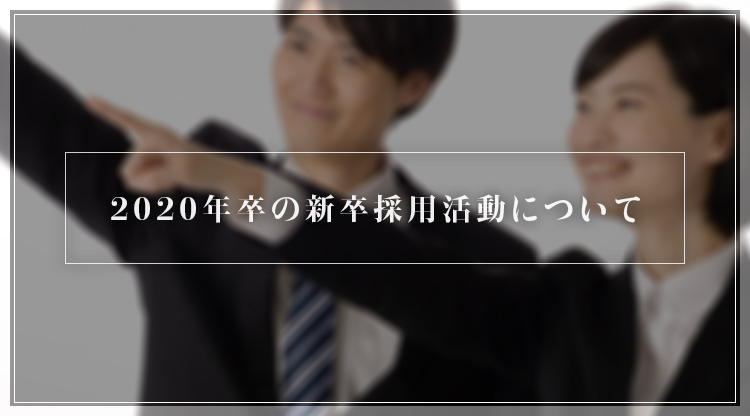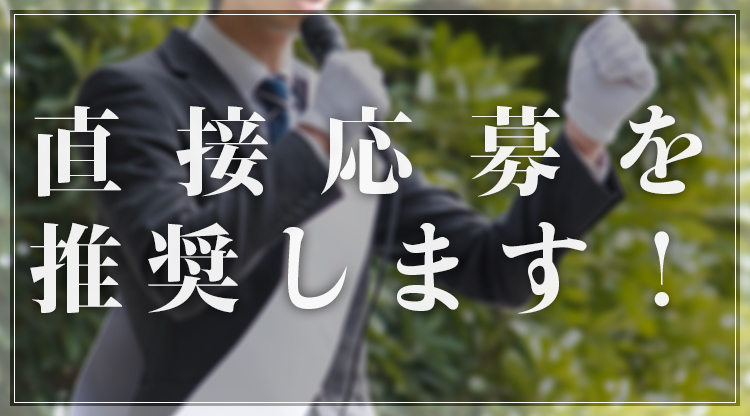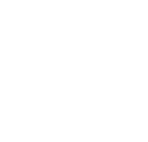
1、平均エントリー数はあくまで目安
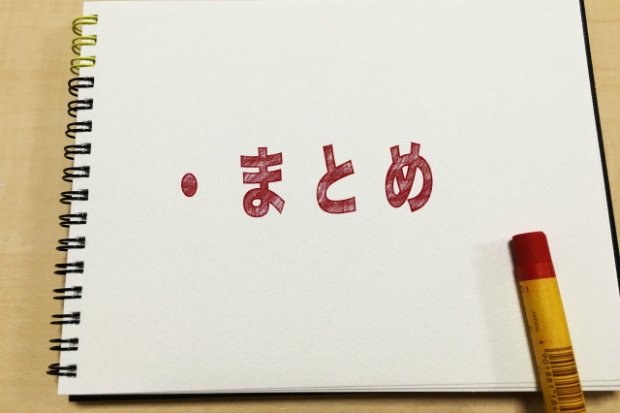
就活はその後の人生を左右する重要な局面です。手を抜いてはいけません。適当に一括エントリーを行うと余計なメールがたくさん来て大切なメールを見逃してしまいます。反対に業界や企業を絞りすぎると選択肢が少なくなり、内定獲得の可能性が低下します。
大切なのは、自己分析、業界研究などをしっかり行い、一つひとつしっかり考えてエントリーすることです。エントリー数に右往左往してはいけません。自分の将来を冷静に見つめ、例えエントリーシートがなかなか通らなくても諦めず粘り強く就活を続けましょう。
エントリーは、どのくらいするものなのかという問いへの答えは、「内定を獲得するまでエントリー」というのが私の答えです。就活の目的は自分に合った企業の内定を獲得することです。エントリー数が増えているのに内定が獲得できていなくても、必要以上に落ち込む必要はありません。最終的には内定が獲得できればいいのです。あなたの真面目で粘り強い行動は、必ず身を結び内定を獲得できます。そう信じ、しっかり就活を行なってください。