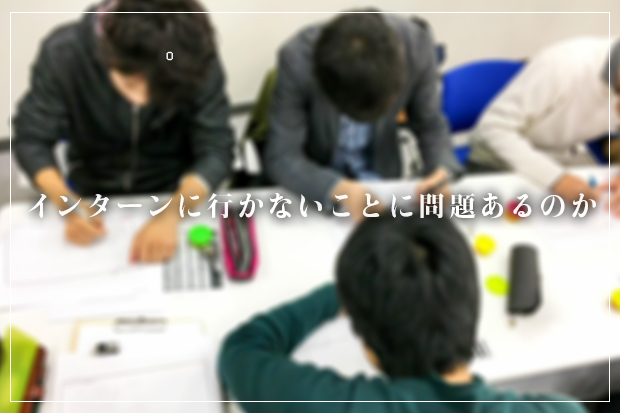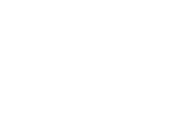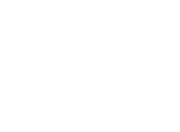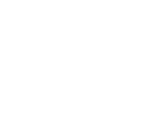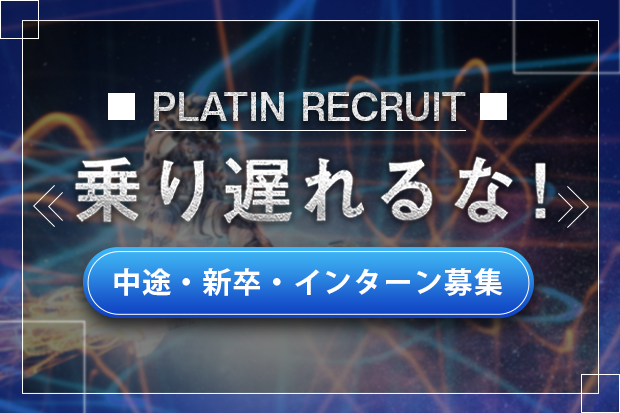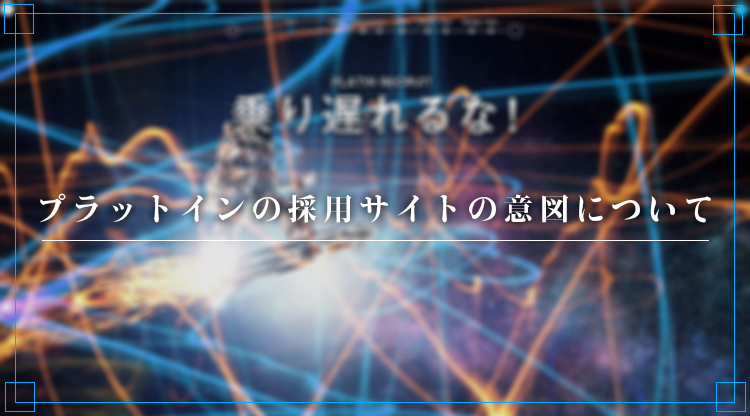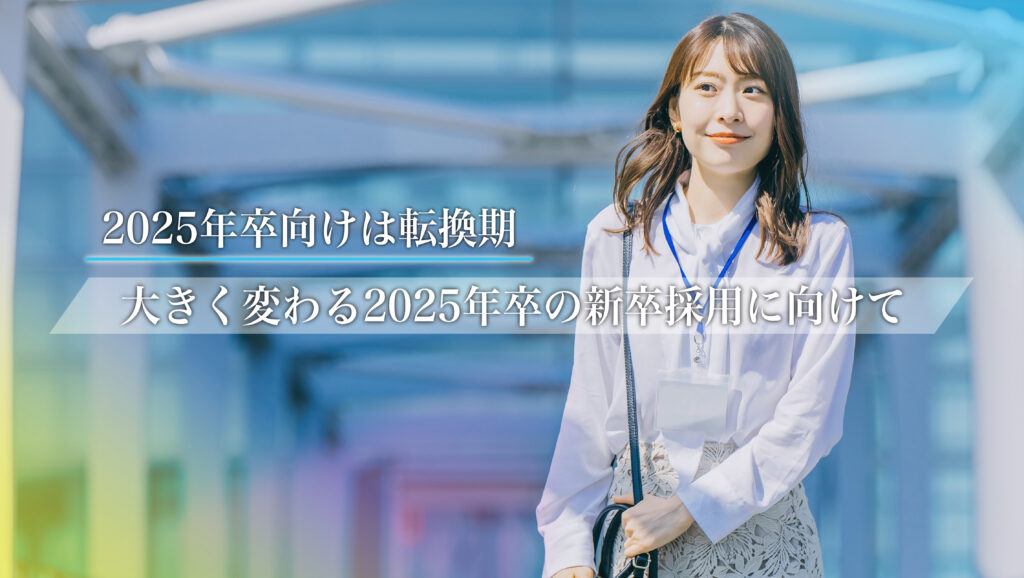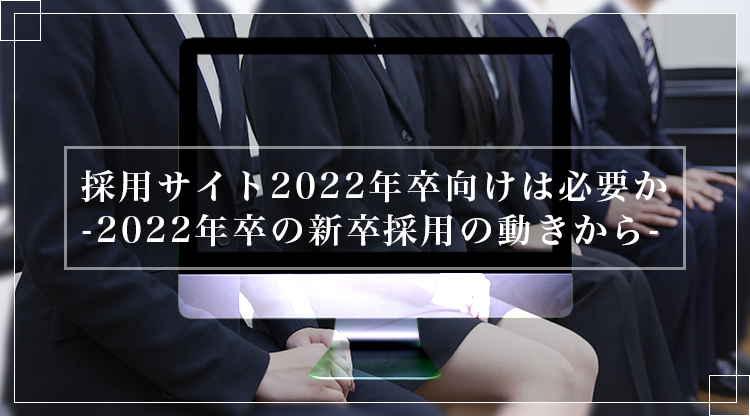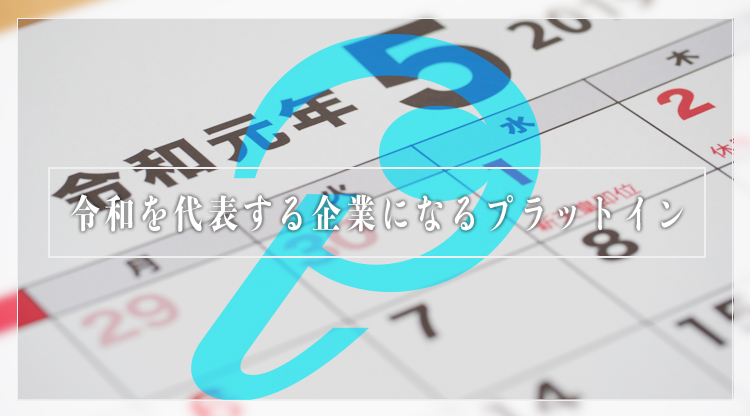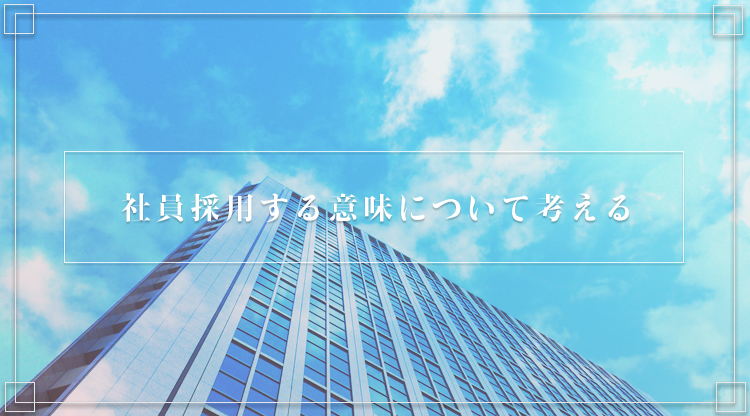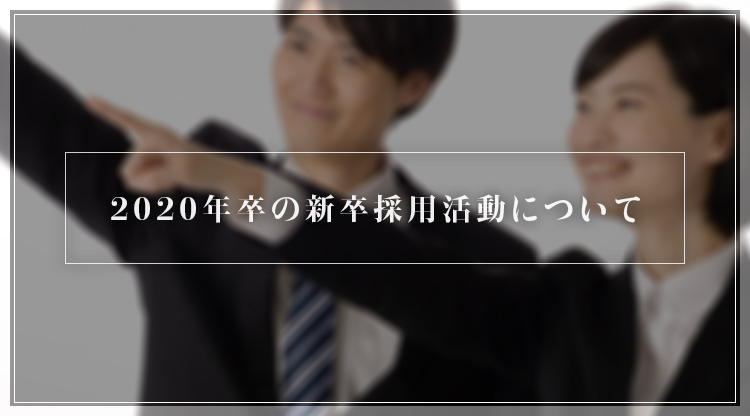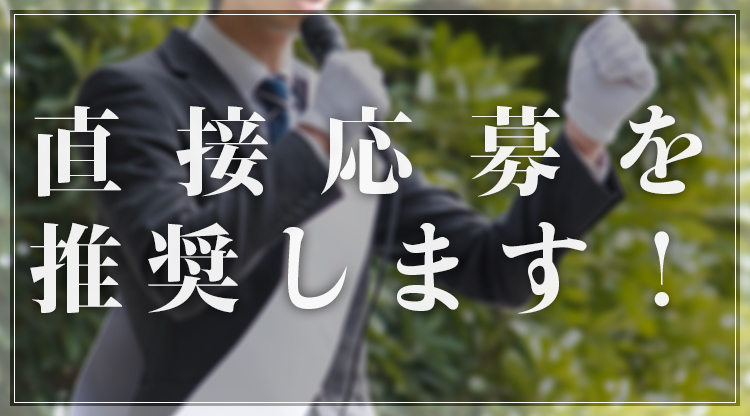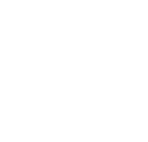
1.企業がインターンを導入する理由
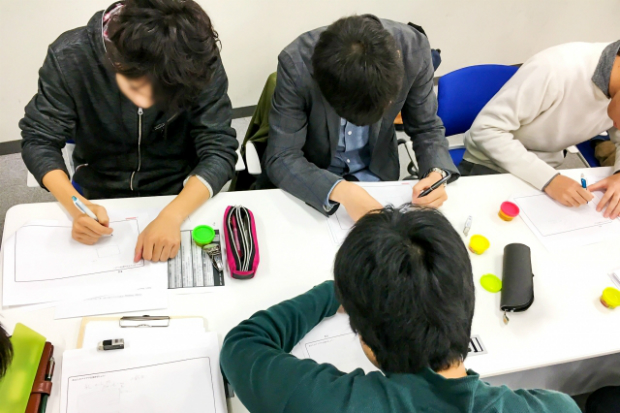
就活生のみなさんがインターンシップへ参加する理由は、
「実際の仕事内容を知りたいから」
「企業風土を感じたい」
「参加した方が選考に有利と聞いたから」
と言った理由からの参加が多いかと思います。
では企業側がインターンシップ制度を実施するのはどんな理由からでしょうか。
「有能な学生を抱え込みたい」
「内定後、実際の仕事内容が想像と違う、という理由からの内定辞退、入社後すぐの退職を防ぐため」
「自社を広くPRする」
という目的からのようです。
自社にマッチした学生を早い段階で囲い込んでおきたい、と考えて実施している企業がほとんどでしょうが、インターンシップを導入することで門戸の広い企業としてイメージアップが望めることもあり、インターンシップそのものというよりはインターンシップに付随するイメージのために行っている企業も多いです。