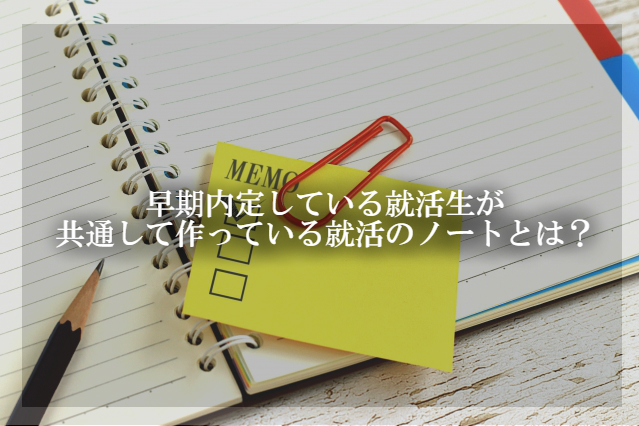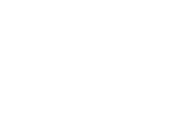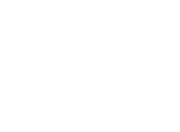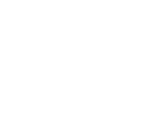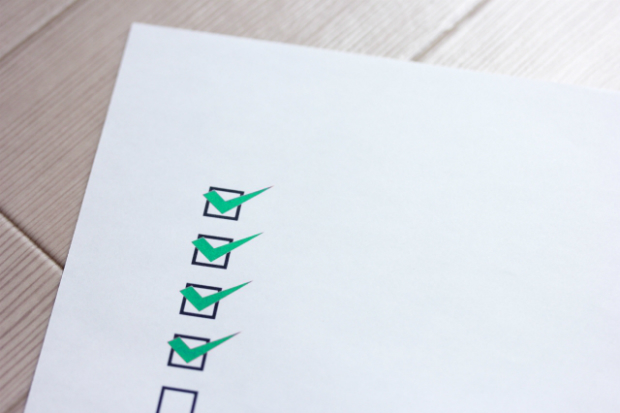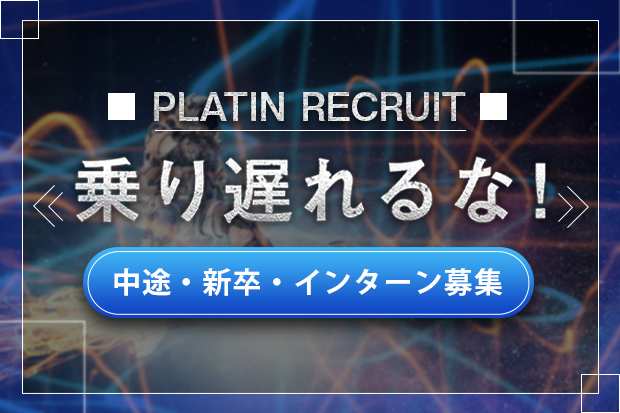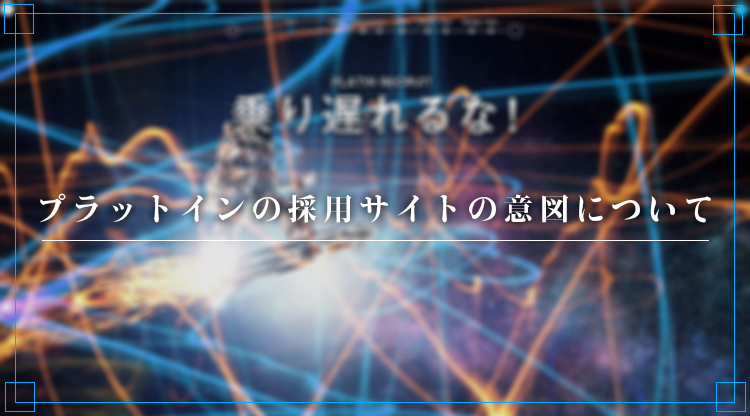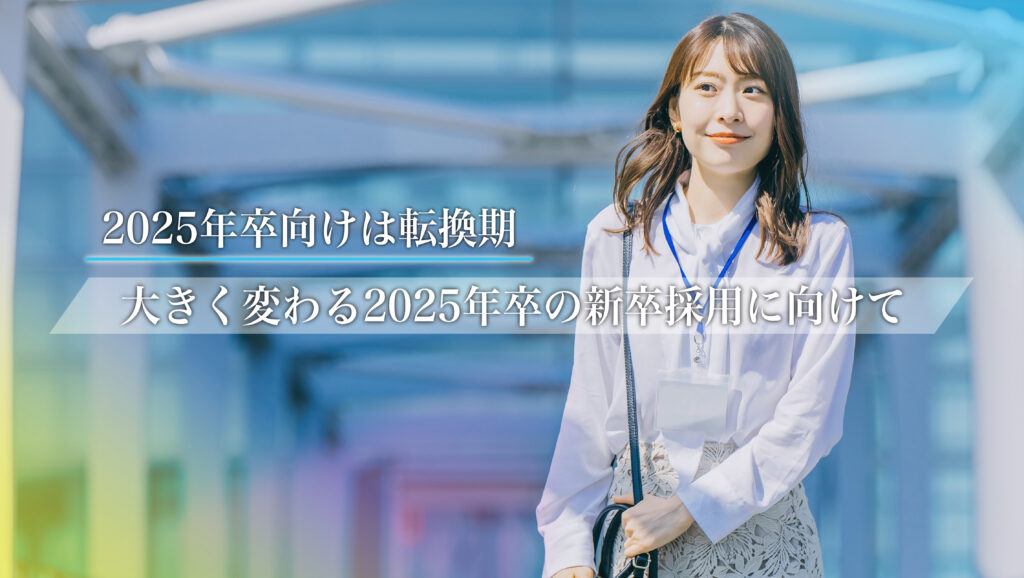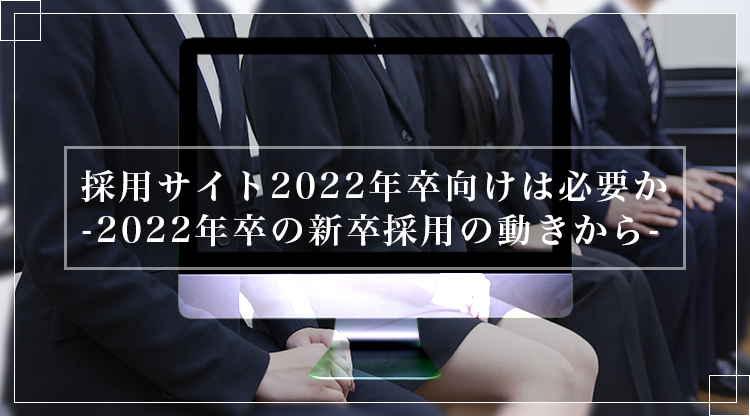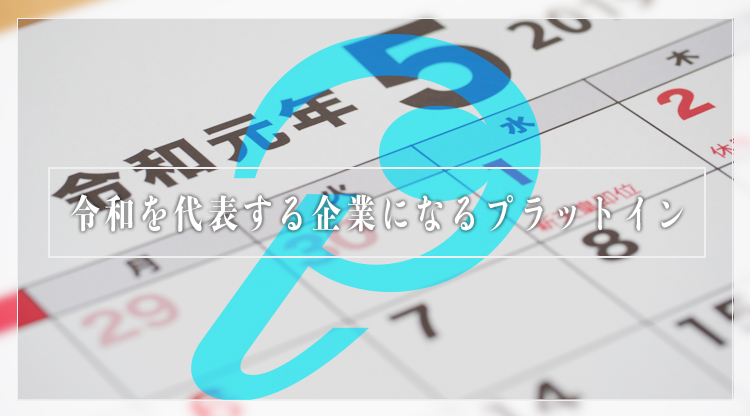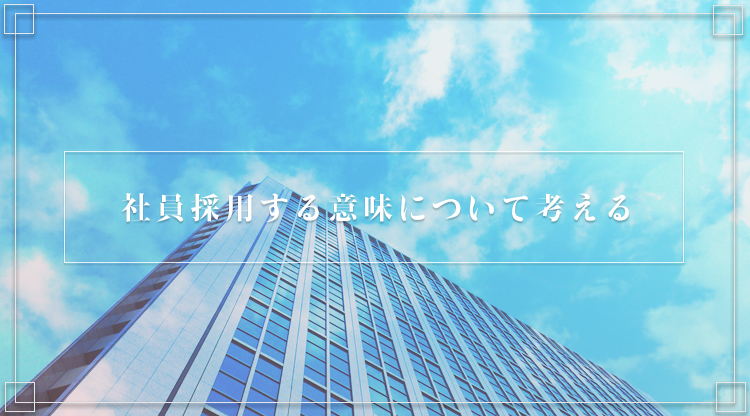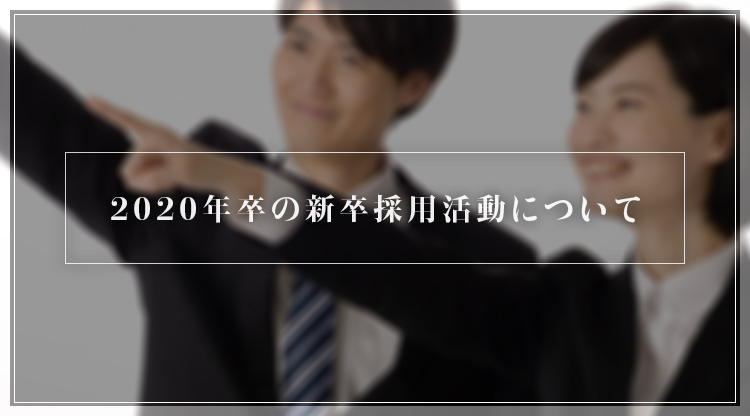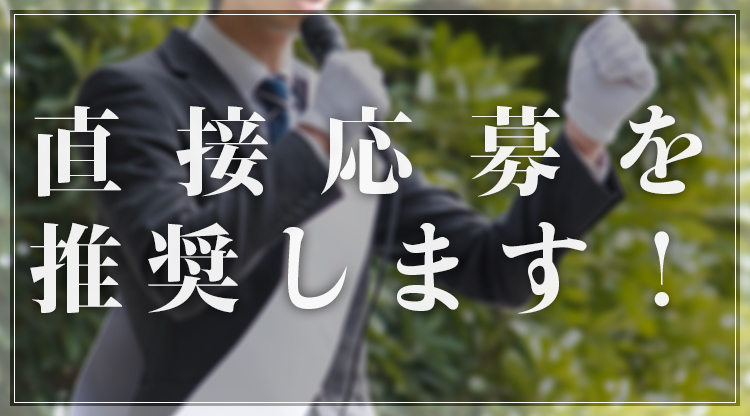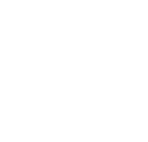
1.早期内定者の就活のためのノートとは?

早期内定者にはいろいろな共通点があります。その一つが、就活のためのノートを作っていること。この就活のためのノートには“これ”という定義はありません。つまり就活生の数だけ、就活のためのノートはあります。
早期内定者には、そのノートの作り方にさまざま工夫を凝らしています。その工夫の説明をする前にまず、一般的に就活のためのノートと言われているものは、どのようなものなのかをご説明します。
まず就活のためのノートとは、当然ながら就活のためだけに作られたノートになります。実は私も新卒の就活のときはもちろん、第二新卒の就活やそれ以降の転職活動のときも就活のためのノートを作成していました。
今になって思えば、そのおかげで超氷河期と言われた時代も、数年前の求人倍率が非常に低かった時代も、就職ができたのではないかと思っています。